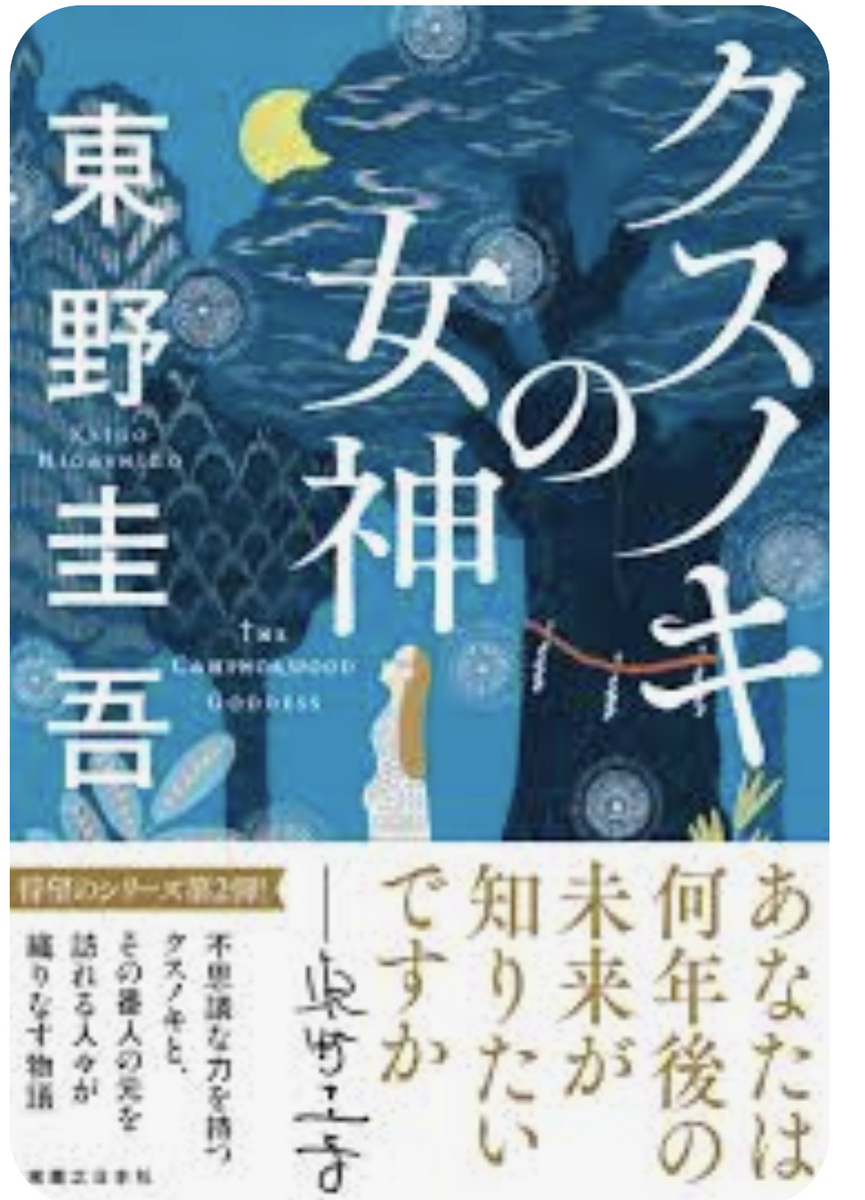
2024年6月5日に発売された東野圭吾の『クスノキの女神』を読んだ感想です。
前作『クスノキの番人』の続編であると知らずに読み始めましたが、十分に楽しめました。以下、ネタバレを含む感想です。
キーワードは「記憶」記憶を失うことへの不安や恐怖を抱えながら生きている人が登場する。その原因は軽度認知症(MCI)、脳腫瘍であったりさまざまだ。病気になった人、その家族しか体験できない悩みや感情に触れられた。
印象に残ったところは2つある。1つは登場人物が病に対して不安を抱えながらも前向きに毎日を過ごしていることだ。
例えば脳腫瘍で脳の一部を切除した男の子。昔の記憶はあるものの、新しいことを覚えられない。
夜寝て次の日の朝になると、昨日誰と合い、何を話して、何をしたのかを全て忘れてしまう。新たに交友関係を作ることが難しい中で、日記をつけることで、昨日の自分と体験を共有している。
2つ目は人との出会いの大切さだ。ただ出会うだけでは駄目で、人の悩みを聞いたり、価値観を共有して共感したり、自分の今後の行動に影響を与えるたりするのが大切だと思った。
少年たちがクスノキの女神にまつわる物語を作る場面がある。困難にみまわれ苦しんだ1人の少年が未来を見通す事ができるクスノキの女神の元へ訪れるストーリーを作るなかで、「未来を知る事はそんなに大事な事なのか?」と疑問が投げかけられる。
その直後に主人公の元に電話が。主人公の叔母からの電話だった。今駅にいるのだが帰り道がわからなくなってしまったという。その人は地元では有名な会社の重役を務めてきた人で、普段の話す口調は自信に満ち溢れているのだが、電話口の声は弱々しかった。
日々進行していくアルツハイマーの症状に対する家族の不安や葛藤を知る事ができ、軽度認知症(MCI)をかかえる人の家族はもちろん、全ての人が読んでほしい一冊だった。
65才の5人に1人が認知症になる日本において、自分にとって大切な人が脳の病気になったらどうしたらいいだろうと考えるきっかけになると思って。
![クスノキの女神 [ 東野 圭吾 ] クスノキの女神 [ 東野 圭吾 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8563/9784408538563_1_3.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 1980 円
- 楽天で詳細を見る
![クスノキの番人 [ 東野 圭吾 ] クスノキの番人 [ 東野 圭吾 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7566/9784408537566.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 1980 円
- 楽天で詳細を見る